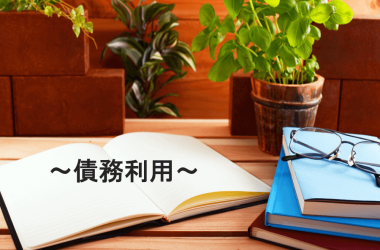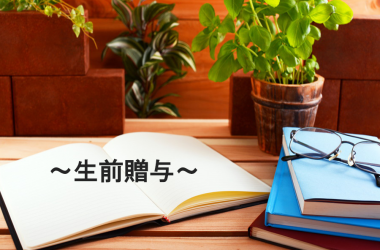相続についての知識を得ておくことも重要
相続後、仲のよかったご家族が仲たがいするという事はよくあることです。
こうしたトラブルが起らない様に、相続についてしっかり決めておくことが必要となります。
人が死亡し、その死亡した方がもっていた財産などを、民法に沿って遺族が引き継ぐ、これが相続です。
ここで問題になるのは、誰が相続するのか、また相続税はどのくらいになるのか?等色々あります。
相続についてしっかりと理解し、相続が発生した時に困る事が無いようにしておくべきです。
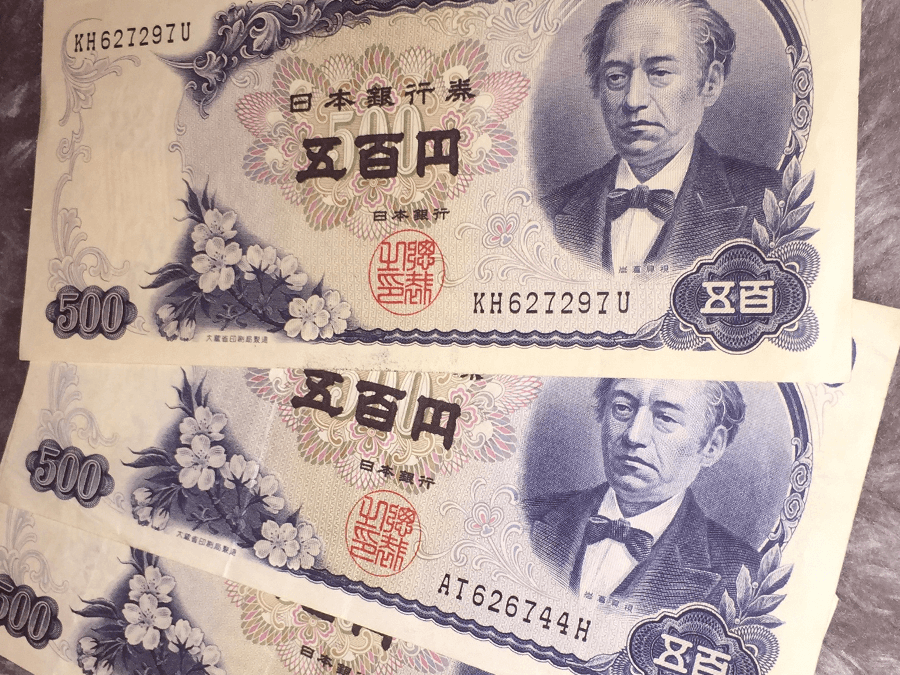
相続税って何?
相続税、贈与税、両方とも、個人に対しての税金になります。
相続税のかかる人については、原則、相続・遺贈、また死因贈与となり、その財産をもたった個人にかかるのです。
基本的に法定相続の場合、個人と個人に発生することになりますが、遺贈、贈与という場合は、贈与する側が自由に設定できます。
つまり、企業などの法人に遺贈、贈与が送られることもありますし、全くの他人に贈与するという事も起るのです。
法人への贈与・寄贈の場合、法人が利益を得ているという事で、法人税の課税が起ります。
基本的に民法では、一定の親族に相続人を限定、その割合についても定めがあるのです。
これが法定相続と呼ばれるもので、法定相続の法律に沿って法定されている相続人が法廷相続人となります。
遺贈とはどういう事を指す?
遺贈というのは、人がお亡くなりになる前に、最終的な意思からの効果により、その人がお亡くなりになってから、意思を実現する制度です。
例えば遺言によって財産をこの人に与えますよという場合も遺贈になります。
遺言の場合、「法定相続優先」となり、遺言を作った人の財産については、その人がお亡くなりになってから遺言書に書かれている通りに処分されていくのです。
財産を遺言によって与える人の事を遺贈者、与えられる人の事を受贈者といいます。
遺贈には大きく分けて二つの種類があり、包括遺贈と特定遺贈です。
包括遺贈は遺産全体の割合を示し遺贈します。
この場合、遺贈者の立場は相続人同様となるため、債務についても包括遺贈の割合によって負担することになるのです。
特定遺贈は遺産の中で特定の目的物について遺贈します。
特定されたその遺産のみ、取得する権利が与えられ、一般的にこの場合は債務の負担はありませんが、もしもあるといわれた場合には放棄するが可能です。
あまり聞いたことがない?死因贈与とは何か
自分が死んだらこの財産をあげるよ、じゃあいただきます、という場合も相続税の対象となります。
財産を無料であげるという贈与者、財産をもらう受贈者とこうした死後の契約について、死因贈与というのです。
この場合、契約書などを作らずとも、当事者がお互いに合意することで成り立ちます。
この場合、人の死亡が原因となって財産を取得すること囲なるので、基本的に相続・遺贈と何ら変わりないことです。
そのため、死因贈与で財産をてにした受贈者は贈与税ではなく相続税の課税となります。