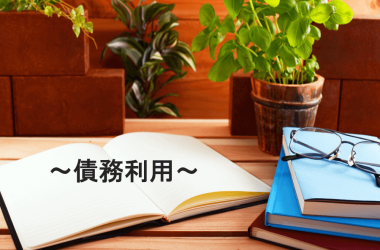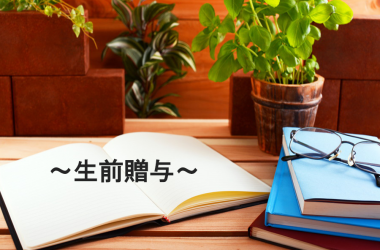相続でもめないためにも理解しておきたい相続の事
親が死亡しその後、遺産相続でもめにもめて兄弟姉妹で裁判という事も、残念ながらよくあることです。
相続についてそれまでは全く何も考えていなかったのに、相続できるものがあるとなると、これがいい、あれがいい、お前はずるい・・と意見が出てきて相続が進まない事もあります。
相続は負の財産、つまり借金も負うことになりますし、相続税なども発生するため、相続について理解しておくべきことはかなり多いのです。
まず理解しておくべきこととしては、相続人について、その順位となります。

相続には大きく二つに大別される
相続人は大きく、「配偶相続人」と「血族相続人」に大別されており、お亡くなりになった方の配偶者については、常に相続人となるのです。
血族相続人については、第1順位として直径卑属の子、代襲相続としての孫、第2順位の相続人として、直径卑となる父母、祖父母がいます。
第3順位としてお亡くなりになった方の兄弟姉妹、代襲相続として甥、姪です。
配偶者の法廷相続分については、子供と一緒に相続する場合は1/2、直系尊属と一緒に相続する場合は2/3、兄弟姉妹と一緒に相続する場合は3/4となります。
代襲相続とは、例えば死亡された方の子供がお亡くなりになり、それによって相続できない場合に、その子にかわって孫が相続することです。
相続分とはどういう意味か?
相続人が一人、という場合はお亡くなりになった方の遺産をその一人の相続人が全て受け継ぐことになります。
こうした相続が単独相続です。
ただ相続人が一人しかいないということはほとんどなく、通常2人以上、複数の相続人がいます。
相続人が複数いる場合を共同相続となりますが、この場合、遺族がどの遺産を受け継ぐのか、これが大きな問題となる事が多いのです。
相続人が複数いる場合、相続人それぞれが遺産を継承する割合の事を「相続分」といいます。
相続分の種類はいくつかあるので理解しておくべきです。
遺言がない相続分で相続の遺産分け基準となる相続が法定相続分となります。
代襲相続人の法定相続分の一つとして、代襲相続分、遺言書指定の相続分で原則法定相続分に優先となるのが指定相続分です。
生前財産贈与、遺贈などを受けている相続人は相続分の修正があり、それを特別受益者の相続分といいます。
また遺産の維持形成に特別な尽力があったという相続人に対し、別途与えられる相続分が寄与分です。
ここでポイントとなってくるのが、被相続人が遺言書を作りそれが正当な物であり相続分が指定されている場合は、指定された相続分優先となります。
そうではない場合には、民法の定めによって相続分が決定し、これが法定相続分です。
遺留分とは何か?
自分で保有している財産についてはどんなふうに処分してもその人の自由、でもこれはその人が生存している間は・・ということになります。
遺言で財産の処分について無制限に決められたのでは困る事も出てきます。
その為民法により一定の範囲で遺留分を相続人に与えて保護するとしているのです。
相続の遺留分というのは、被相続人が自由に処分出来ない財産の割合を示しています。
遺言により遺留分について侵害がある場合、相続人は相続が開始後、その分の減滅請求できるのです。
但し、遺留分の権利がある相続人については、法定相続人の中でも、配偶者と直系卑属、直系尊属とされ、兄弟姉妹についてはないと決まっています。